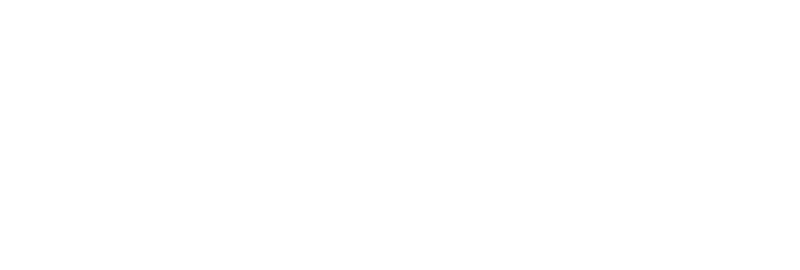「理想の基準」なき診断の壁
1. 導入:チーム分析の3つの視点と、残された最後の課題
チームの機能不全を診断する際、私たちは3つの強力なフレームワークから多くの洞察を得てきました。これらは、チームという複雑なシステムを構造的、優先的、心理的に理解するための地図を提供します。
- IMOモデル: 「構造」の視点。問題の原因がInput(資源)、Mediator(プロセス)、Output(成果)のどこにあるかを切り分ける。
- GRPIモデル: 「優先順位」の視点。課題をG(目標)からI(人間関係)へとどこから直すべきかを示す。
- レンシオーニモデル: 「心理的深層」の視点。すべての問題の根源にある信頼の欠如に焦点を当てる。
これらのモデルを組み合わせることで、私たちは多くの課題を解決できます。しかし、これらレガシーモデルには、共通して乗り越えられない決定的な限界があります。
2. 総括:レガシーモデルが抱える「決定的な共通限界」
IMO、GRPI、レンシオーニのすべてに共通して欠けているもの、それは「客観的な理想の基準」です。
チームが「うまく機能している」かどうかの評価が、最終的に「成果が出たか(Output)」や「メンバーが満足したか(Mediator)」という結果論や主観に頼らざるを得ないのは、この理想の基準がないからです。
IMOモデルにおける「Inputの曖昧さ」
IMOモデルはInput(資源)の重要性を説きますが、「理想的なInputとは何か?」を定義できません。
- 問題点: メンバーのスキルや個性といったリソースが「チームにとって適切に分散配置されているか」を測るための定規がないため、リソースが偏っていてもそれが「機能不全の初期条件」であると診断できません。
GRPIモデルにおける「役割評価の限界」
GRPIモデルは役割(R)の明確さを求めますが、その役割の「設計そのもの」が正しいかを評価できません。
- 問題点: たとえば、チーム内に「ブレストが得意な人」が一人しかいない場合、役割(R)を明確にしても、その人物に過度な負荷がかかり、他のメンバーの潜在的なリソースが使われていないという状態を見抜けません。これは、「本来あるべきリソース分散の理想形」が分からないからです。
見逃される「見えない機能不全」
この基準の不在が、現場で最も深刻な問題を見逃します。
【見逃しがちなケース】 「プロジェクトは成功し、成果(O)は出た。しかし、それは一人の優秀なメンバーが全工程を一人で担い、他のメンバーのリソースを抑圧した結果だった。」
この場合、成果(O)は良いため、IMOでもGRPIでも「チームは機能している」と誤診されがちです。しかし、リソース配分という初期条件から見れば、そのチームは持続可能性のない、極端に偏った機能不全に陥っています。
3. 限界の突破:IMOの論理に乗せる「客観的な定規」
私たちは、IMOのI(Input)に、客観的で普遍的な「理想的なリソース分散の基準」を組み込むことで、このレガシーモデルの限界を突破します。
この「基準」こそが、古代マヤ文明のツォルキン暦が持つ四方位の概念です。
【新しい診断の論理構造】 チーム分析に、「普遍的なリソース分散のバランスがとれた状態こそが理想である」というInputの絶対的な定規を導入します。これにより、チームの活動を結果論ではなく、「理想的な状態からどれだけ乖離しているか」という客観的な視点から診断することが可能になります。
4. まとめ
IMO、GRPI、レンシオーニは素晴らしい地図ですが、地図に「現在地」と「目的地」の基準がなければ迷子になります。
私たちが求めているのは、「チームのリソースの理想形」という、動かない客観的な基準です。
次回の記事では、この古代マヤの普遍的な知恵を、IMOの論理構造に組み込み、結果論に依存しない、課題解決に直結する新しいチーム診断フレームワークを具体的に提案します。